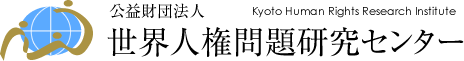創立20周年 記念講演会

基調講演 国際社会における日本のあり方
元国連事務次長 明石 康 氏
ただ今ご紹介にあずかりました明石でございます。今日、この世界人権問題研究センターの創立20周年の記念の集まりにおいて基調講演をさせていただくという、大変光栄な経験をする機会を得まして心から喜んでおります。
私はこのセンターにおいて19年前にも話をさせていただく機会がありました。そのときには、このセンターの恐らく終わりのない課題として、「違いを喜べる心」という題でお話をしました。しかし、世界をながめてみますと、ウクライナにおいても、シリアにおいても、イラクにおいても、アフガニスタンにおいても、また、われわれの住んでいる東アジアにおいても、「違いを喜べる心」には甚だ遠い状況が存在しております。
先ほど上田正昭先生が大変格調の高いお話のなかで、われわれの住むこの日本においてもまだまだ差別の問題は遠い存在にはなっていないことを、先生としては恐らく悲しみの心を込めてお話をされました。
私は、先ほどご紹介にありましたとおり、私自身の長い国連経験に基づきながら、上田先生のお話に比べれば雑駁な話になると思いますけれども、身近な体験に基づいてお話して、このあとの討論の時間において、京都大学の中西寛先生とともに、皆様からのご質問なり、コメントなりを頂戴したうえで、さらに説明する機会があれば幸せだと思っております。
日本が国連に加盟したのは1956年12月18日です。私はそれから2カ月も経っていない翌年2月から、国連事務局内の政治安全保障局というところでちっぽけな部屋をもらって仕事を始めたのを思い出します。
ほんの腰掛けくらいで終わるだろうと思いました国連の仕事は、それから約40年間続くことになりました。正確にいいますと、35年間は国連事務局において国際公務員として仕事をしました。残りの5年間は日本政府国連代表部において参事官、公使、大使として仕事をしました。その期間は国家公務員であったわけです。1979年に国連に再び戻りまして広報担当の国連事務次長、次いで軍縮担当の事務次長を務めました。そのころ冷戦が終わり、カンボジアにおける和平の機が熟したということで、92年から1年半にわたってカンボジアにおける国連平和維持活動の責任者として、カンボジアの民主的な新生国家誕生のプロセスに関わりました。
カンボジアの仕事を何とか終えて国連本部に帰って、ほっとして間もなく、1994年1月から95年11月まで、ほぼ2年間にわたり、バルカン半島の旧ユーゴスラビアが民族紛争のただ中に立たされたとき、国連最大の平和維持活動の責任者として仕事を仰せつかりました。それから国連本部に帰り97年の暮れに国連を退官するまで、人道問題担当の事務次長を務めました。
合計約18年間事務次長をさせられました。新渡戸稲造さんは国際連盟において約6年間事務次長をされたわけですけれど、私の場合、長さにおいては新渡戸さんの3倍ぐらい国連事務次長を務めることになりました。
約40年間の国連生活において、日本で生まれ育った1人として、日本国憲法の掲げる理想と国際連合が掲げる理念のあいだの矛盾に、おまえは苦しまなかったか、悩まなかったのか、という質問をよく受けます。私は自分がちょっと鈍いせいかもしれませんけれども、また楽観的な性格によるものかもしれませんけれども、はっきり申しあげて、あまり矛盾に苦しむようなことはなかったといっていいと思います。
1956年12月国連加盟のときの重光外相の加盟演説を、私はフレッチャースクールという大学院大学におりましたので、国連に参観旅行に行って聞く機会に恵まれました。決して英語としては上手な演説ではありませんでした。しかし内容的にはとても素晴らしい、その後の日本の外交政策を判断する1つの基準ともいえる鮮やかなビジョンがそこに盛り込まれていたのを覚えています。
重光演説の基調は、これからの日本は国連において、日本国憲法前文に規定している、「国際社会の名誉ある1員」としての覚悟で当たるのだということで、国際連盟を日本が脱退したのは1933年でしたけれども、それから23年間国際機構から欠席した空白期間を経て国際社会に復帰した喜びと晴れがましさと覚悟を、重光さんは演説の中で表しておられたと記憶しております。
私は、戦後の日本の平和主義は基本的に正しいものだと考えております。それは何よりも、戦前の軍国主義、超国家主義とか対外侵略に対するわが国国民の厳しい反省の産物であったからです。
戦後の平和主義は憲法前文と憲法9条の両方に表れています。憲法前文は「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記されています。
憲法9条は2つの項目から成っていて、その第1項においては、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という戦争放棄が謳ってあり、第2項においては、「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と記されています。
憲法9条をどのように解釈するかについては国民のあいだでも意見はいろいろと分かれていると思います。しかしながら、私は9条から必ずしも非武装平和主義を導きだすことはないと考えます。
戦後の日本人はアジアにおけるスイスを夢見た時期もありました。しかし皆さんのなかでスイスに旅行された方は多いと思いますが、アルプスの美しい山々のふもとにトンネルの穴が各所に掘ってあるのに気づかれた方もあると思います。この穴は多くの場合、スイスの軍が戦闘機を山腹に隠しておくために使われています。スイスの場合、非武装中立主義ではなくて、武装中立主義です。スイス国民が必要と考えた最小限の軍備は、きちんと持つという考え方に立っているわけです。
とりわけ、われわれが位置する東アジアにおいては核兵器を持っている国がいくつかあります。中国がそうであり、ロシアがそうであり、日本と同盟関係を結んでいるアメリカがそうであり、また核不拡散条約に違反して北朝鮮が核兵器を持つにいたっているわけです。そのような厳しい現状があります。
1950年に朝鮮戦争が勃発し、そのときにはいわゆる国連軍なるものが、たまたまソ連代表が欠席していた安保理事会において決定されました。これは国連軍といわれますけれど、本来の国連憲章が規定した国連軍ではなく、今の表現でいえば国連の承認を得た多国籍軍といえるものです。ソ連代表が安保理に戻ってきてからは、問題は安保理事会から国連総会に移されて、1950年11月3日には国連総会において、「平和のための結集」決議が採択されました。安保理のような強制的な決定権はないわけですが、国連総会による決議の形で朝鮮戦争への国連の関与が続けられることになりました。
国連のPKO活動は1948年に中東地域で、停戦の監視をするため始まりました。56年には第2次中東戦争(スエズ危機)があり、エジプトがスエズ運河を国有化したのに憤激したイギリスとフランスとイスラエルの3国がエジプトに侵攻したわけですが、これに対して国連側としては何とか対処しなくてはいけないというので、かなり大規模な国連平和維持活動が始められることになりました。国連憲章には平和維
持活動(PKO)に関する規定はまったくないのですが、国連は国際社会の必要に迫られてPKOをつくったのです。
つまり、国連が示した柔軟な態度、実践的な対応の仕方は、その後もいろいろな形でみられます。人権活動に関してもそういうことがいえるのではないかと思います。PKO活動に関しては、国連はいろいろな形で脱皮し新しい段階に進んでおり、停戦監視型の第1世代のPKO活動から、戦争を経た新生国家の誕生を助けるカンボジア型の第2世代、実力行使のソマリア型の第3世代を経て、アフリカの1部で展開する
強力な第4世代PKO活動という、在来の小型兵器から武装ヘリコプターとか、近代的な戦車まで使う最近のPKOに至る、多角的な展開をみせているのに注目すべきではないかと思います。
戦後日本民主主義の中道的かつ穏やかな歩みと国際協力は、今までの6十数年において多角的な形に及んでいますけれど、これで十分かどうかということになりますと、私は決して十分ではないと思います。
ともかくも、今のように日本と中国との関係がささくれだった難しい状況になる以前には、中国の指導層が日本の戦後平和主義をきちんと前向きに認識していた時期がありました。例えば2007年において、当時の温家宝総理がわが国の国会での演説の中で、日本の戦後の歩み方、平和主義、また中国に対する援助について評価するとはっきりいっております。温家宝総理は、「実は日本の国会で自分は演説したのだけれど、この放送は中国で自分の母親がそれを見て、それに同意してくれた」とコメントしています。その翌年、日中共同声明において、胡錦濤主席も、戦後日本の歩みを評価することを言っております。
私は、ここ数カ月国内で大変激しい、集団的自衛権をめぐる活発な論争があったことにふれたいと思います。はっきり申しあげて、私にはこの複雑な論争はよく理解できません。国連憲章には第51条があり、これは国連憲章の他の規定とやや違うトーンで書かれているのですが、そのなかに「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が記されています。国連加盟国が自国の安全に危機を感じたときに、安保理事会が行動をとるまでの期間において、個別的ないしは集団的な自衛の権利を行使してよろしいという項目があります。「固有の権利」と訳されている言葉は、英語では「inherent right」という言葉になっていますが、フランス語では「le droit naturel」という表現であり、「自然権」といってよく、普通の権利よりもっと重いものです。
戦前の日本は、ほかの国もそうであったわけですけれど、自衛権をときに誤用し、乱用する時期があったことをわれわれは忘れることはできません。また、ミサイルとか核兵器の時代になった現代において、自衛権はどのように行使されるべきかについては、国連において議論がなされました。
今の潘基文事務総長の前のコフィー・アナン事務総長のときに、彼は「ミサイルや核兵器の時代には、そうした武器が自国に到達するまで自衛権は行使してはいけないということにはならないだろう。しかし、ミサイルが発射国にあってまだ発射されない段階において、それを攻撃して破壊する予防的自衛権が生じるかについては、自分は賛成できない。」ということをいっております。つまり、核兵器を積んでいるかもしれないミサイルが自国に到達する前に自衛権は行使されうるけれど、それを拡大解釈するのは許されないだろうと、アナンは反対していました。
そういうふうに、明らかに迫り来る明白な危険にどのように対処することができるのか、どういう場合に防衛手段が法的に発動されてよいのかについては、はっきりした答えはないと思います。
現代のように多角的な国際関係が存在する環境のもとにおいて、私は個別的自衛権と集団的自衛権は峻別できるものではないのではないかと考えます。同時にできるだけ拡大解釈ではなく、厳密な自衛権の解釈に基づき、この権利は行使されなくてはいけないのは明らかです。
それとは別の概念で「集団安全保障」ということが、国連が発足した約70年前から現在まで使われてきております。この「集団安全保障」は、「集団的自衛権」とはまったく違うものです。国連の存在の基盤にあるのが、安全保障のような大事な問題はできるだけ集団的に、みんなでほかの国と一緒に考え行動すべきであるという基本的な理念が貫いているのですが、残念ながら、集団安全保障は、国連憲章第7章に盛り込まれていますけれども、不十分にしか実現しておりません。
本当の意味での国連軍も存在していないのです。国連ができて2年ほどの間に、アメリカとソ連の間、アメリカとイギリスとかフランスの間にさえも、どういう規模の、どういう性格の国連軍をつくればいいかについて意見の相違が明白になりました。ですから国連軍は本来の形ではできていないのです。
湾岸戦争があったときに各国が安保理決議に従って集まって、侵略を行ったサダム・フセインのイラクに対処し、侵略されたクウェートを国際社会として守る集団安全保障行動をとりました。この場合の国連軍も、はっきり申しあげると寄せ集めの軍隊であったといえるでしょう。
そういう国連軍ができた場合、わが国はどういう行動をとるかについては、日本としては白紙の状態におかれているのが現実であると思います。日本が国連に加盟した1956年12月の重光演説のなかでも、「国連憲章の特定の規定に日本は留保します。この条項は日本として守ることはできません」とは1言もいっていないわけです。国連憲章第4条は、国連に加盟する国は、「国家」であり、「平和愛好国」であり、また国連憲章の規定を忠実に守る「意志」と「能力」を兼ね備えていなければならないと規定しています。ですから、ここには国際法の大家の方々がおられるので私の意見をいうのは忸怩たるものがあるのですけれども、国連憲章第7章の集団安全保障は大きな宿題として今も世界各国に答えを迫っていることを付け加えておきます。
ところで、今年は2014年で、第1次世界大戦が始まってちょうど100年になる年です。第1次世界大戦は第2次世界大戦に勝るとも劣らない多くの犠牲を世界各国に迫ることになりました。
私は1994年から95年まで2年近く、旧ユーゴスラビアにおける民族紛争のただ中に、3万人を超える平和維持活動の国連側責任者として参加することになりました。その間、旧ユーゴスラビアのボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの街を散歩することがありました。散歩の途中で、第1次世界大戦の引き金になったオーストリア皇太子暗殺現場に立つことがありました。セルビア人の若いナショナリストが、その土地を訪れたオーストリア皇太子、当時はオーストリア=ハンガリー帝国ですけれども、その皇太子を殺害し、それがきっかけとなってオーストリアがセルビア人青年の属するセルビアに宣戦布告をし、他方、ロシアはセルビアと結びついていたので、オーストリアに宣戦布告をする。オーストリア側についていたドイツはオーストリア支援のため宣戦布告をするという状態になり、さらにドイツの侵略主義を恐れていたフランスとイギリスが、反対の連合国側に立つことになり、究極的にはアメリカやわが国も連合国側に参加する形になり、世界中の有数の国々が参加する、4年以上の大変激しい戦争となって、900万人以上が犠牲者になりました。今日お話になる中西先生のほうがはるかに熟知しておられることですけれども、そういう第1次世界大戦が発生したわけです。
そうしたことが再び起きないように期待を込めてつくられたのが、国際連盟です。しかし国際連盟も、有力国が参加しなかったというような大きな欠陥のため、第2次世界大戦の勃発を止めることはできなかったのです。このことに対する真剣な検討の結果、連盟の弱点を補強して、今の国際連合がつくられ、今や70年になろうとしています。
しかし、戦争の性格はかなり違ってきているのではないかと思います。特に冷戦が終わった1990年以降には国際的な国と国との紛争は確かに少なくなってきたと思いますが、その反対に国内紛争の方がきわめて増えてきています。
日本のように民族的なまとまりのいい国はむしろ例外に属するのであって、多民族国家が世界には圧倒的に多いわけです。ときにはソマリアのような、民族は1つですが部族が非常に多いような国もあります。それらの国は、言語とか文化とか宗教の違いが大きいので、それをきっかけに国内紛争が激化する場合が増えております。
このような1国内の民族間対立は、政府と政府の正規軍による戦いよりもややこしく複雑なのです。正規軍のほかに不正規軍があり、ときには犯罪者集団や外国軍隊も混じってくるので、旧ユーゴスラビア紛争などでも国連は大変苦労しました。国連としてはこの紛争に関係したくなかったのですが、ヨーロッパ諸国がぜひとも来てほしいというので、国連は嫌々ながら関係させられたわけであります。究極的には国連では処理できなくなって、アメリカを中心とした北大西洋条約機構、いわゆるNATOが、国連にとって代わることになりました。現在ではイスラム国とかアルカイダとか、国境を越えたテロリストの問題が不気味な存在として国際社会に立ちはだかっております。
WCRPという、京都にも関係の深いNGOがあります。それは、世界宗教者平和会議(World Conference on Religion and Peace)の略ですが、世界の宗教者、宗教団体の多くが一緒になって、「平和の問題について話し合い、行動しなければならない」という立場から結成されたものです。先週、東京の国会すぐそばの参議院会館において、自民党や民主党などが中心になって超党派の形で、WCRPの人たちと懇談会をもつということで、私も参加して話をしてまいりました。
本来、国家と宗教とは全く関係がないという立場に立ってきた戦後日本ですけれど、そういってもいられないということです。アメリカや、スカンジナビア諸国、オランダなど他の国々も参加しているわけですし、宗教者のNGOとか各国政府が、国連と協力する形で平和維持に参加すべきだという考えが強くなってきています。
その会合で、私は旧ユーゴスラビアPKOの話にふれました。1991年に、バルカン半島にあるクロアチアのある小さな農村において、そこに住んでいるセルビア系農民とそこに入ってきたクロアチア人警官との間の小さな紛争がきっかけになってそれが拡大していきました。セルビア人農民が先に発砲したのか、クロアチア人警官が発砲したのが最初なのか、よくわかりません。いろいろな本が出ていますけれども、それぞれの立場から書いた本なので、相手のほうが先に発砲したのだといっています。これが旧ユーゴスラビアの紛争の1つのきっかけであったといえます。私はそれを読み、芥川龍之介の『藪の中』という小説を思い出しました。それは、ある事件を4人の人が目撃し、まったく違う4つの物語を語っているわけですが、この種の民族紛争が増えてきているといえます。
こうした偶発的な事件をできるだけ防止する必要があると思いますし、またそういうことが起きた場合に、ホットラインといいますか、関係する国々ないしはグループの間の意思の疎通をきちんとすることが大事になってきていると思います。
この2、3日のあいだに、2年半ほど首脳会議が行われなかった日中間の会議が再開されることになったのは大変に喜ばしいことだと考えます。その会議において取り上げられることの1つが、危機管理のメカニズムをどう設置し機能させるかということで、この場合、意思の疎通、正確な情報の伝達がいかに重要かを示しているのだと思います。
紛争はこのように偶発的に起こりうるのでありますけれども、そうでない紛争も確かにあります。例えばアフリカ中部のルワンダのケースです。この国は少数民族のツチ族と多数民族のフツ族の2つがあり、フツ族指導層が大変冷徹な形で、この事件を密かに起こす準備をし、かなり計画的にツチ族の皆殺しを策したことが、紛争が起きてからわかってきました。推定70万人から80万人の何の罪もない民衆、女性や子どもが多く巻き添えになっている。現代におけるジェノサイドの悲惨な1つのケースであります。これは偶発的でなく、計画的な紛争の起こり方であります。
また、私自身が関係した自衛権のことを少しお話します。私はカンボジアPKOの責任者として、紛争した4派を公平な立場で遇し、結局、3派は国連と協力してくれましたが、ポル・ポト派が非協力に変わりまして、このポル・ポト派の非協力に非常に悩まされました。
私と軍事部門の総司令官だったオーストラリアのサンダーソン司令官は、国連PKOはある程度の小規模な武装はしているけれども、武力行使というものはできない。これは安保理決議を読んでもできないことになっていますし、各国からの寄せ集めの軍隊ですので能力からいっても本格的な戦争はできないという判断の上に、私とサンダーソンは立っていました。
しかしながら、ポル・ポト派よりも大きな2万人の国連軍がいましたので、寄せ集めの軍隊であっても、ある程度武力をもっているのだからポル・ポト派制圧は正しいことだし許されることだとフランス出身のロリドン副司令官は言いました。国連の若手の血の気の多い職員もそうだと言い出しました。特にがっかりしたのは、マスコミ関係者がわれわれの慎重な態度を批判したことです。私は、時としてマスコミは血を好み、正義の側に立とうとする傾向があるのだと感じて、失望しました。この事件は鉄のカーテンになぞらえて、「竹のカーテンに明石とサンダーソンは怯んだ」という形で報道されました。
旧ユーゴスラビアPKOに関しては、国連側と北大西洋条約機構側、つまりNATO側との間に「2重のキー」というものが存在していました。国連とNATOのキーが同時に作動しないと、NATOによる空爆が行われない形になっていたのです。私には国連側のキーを与えられたわけですが、できるだけ武力の行使は慎重にやるべきだ、われわれの与えられている国連決議はその点曖昧でしたが、現地の責任者として国連側の武力を過大視することは許されないだろうと考えて慎重だったわけです。
しかしながら、私は国連要員が現実に生命の危険にさらされた場合には、その国連要員を攻撃している戦車とか大砲に対して、ピンポイントで国連側がNATOに行動を要請することは、明らかに誰の疑いもなく自衛の行為ですので、そういうことには15~16回私は賛同して、空爆が行われました。しかしながら、それ以上の本格的な空爆は明らかに政治的な行為でありますので、非常に慎重に行動しました。
アメリカの国連大使で、その後国務長官になったオルブライトという女性がいます。この人は回想録のなかで「病的に中立だった」文民代表として私のことを描いているのです。「病的に」というのはちょっと余計だと思いますけれども、とにかく慎重すぎる態度をとったと私を批判しました。しかし、この回想録は、NATOとかアメリカの圧力で国連PKOが本格的な空爆に踏み切った結果として、340人の国連要員がセルビア軍に人質として捕まって悲惨な経験を味わうことになったと書いてあります。それを読むと、あたかも慎重であった私の態度のほうが正しかったようにも読めるわけです。
国連の中立性と善悪の判断はどうあるべきか、これまた悩ましい問題であります。2000年には、アルジェリア人で私の非常に尊敬する同僚であったブラヒミという、国連事務総長代表をいろいろな紛争地域でやった人のレポートが出ました。伝統的なPKOにおいては中立性とか不遍性が大事であったけれども、善と悪とを峻別すべき場合もあるので、そういう場合は国連としても善の側に立つべきであるという立場をとっております。
私は昨年、ハーグにある国連のつくった法廷において、カラジッチというセルビア人勢力最高指導者の裁判で証言をしました。来年は同じハーグにおいて、旧ユーゴスラビアPKOのときに起きたスレブレニツァというところの悲劇に関して国連の責任があるのかないのかということに関するシンポジウムにおいて話をすることになっています。そういう意味ではこうした問題について最終的な答えは必ずしもまだ出ていないわけです。
私は日本の国連主義とか平和主義という戦後の立場は基本的に正しいけれど、いろいろ新しい国際情勢もあって、具体的な状況のもとで、人権の問題をどう考えるか、武力の行使についても、答えは必ずしも1つではなくて、いろいろ考えるべきことがあるだろうと思います。それぞれの政府、それぞれの国際機関においても、できるだけ多くの人を巻き込んでいろいろな立場からこのような問題について一緒に考えてみることが大事であろうと思います。
日本としてやるべきこと、その責務とか役割を考えればたくさんあるわけですけれど、私は開発とか人道主義を中心とした政府による援助活動、いわゆるODAを駆使した日本の平和外交を引き続き展開することは正しいと考えます。残念ながら、ODAについて、1980年代において日本は世界第1位だったのですが、今はその頃に比べると半分以下になっているのは残念なことだと思います。
国連の平和維持活動も、いろいろ問題や弱点はありますけれど、国連らしい1つの大事な活動であります。今も南スーダンに自衛隊が1個大隊派遣されていますが、大変良い活動をして感謝されています。こういうものに多角的に参加するのは正しいと思います。
それから先ほど申しあげた集団安全保障についても、ケースは少ないのですけれども、できることがあったら、それを前向きに考えてみることも大事だと思います。
私自身はスリランカ問題担当日本政府代表として現在、スリランカ政府をより民主的、より人権に配慮する、多数派と少数派との共存にも努める方向に導くように微力ながら努力をしております。しかしながら、欧米がやっているようにそれをおおっぴらに宣伝したり、スリランカ政府に説教をするような態度をとらずに、できるだけ非公式な形で説得し、政府と反対勢力の間に橋を架けることに努めるのが日本らしいやり方であろうと考えています。スリランカ民族紛争に関しては、ノルウェーとかアメリカと協力して行った時期があります。タイ南部とかフィリピン南部のミンダナオとかミャンマーなどにおいても、日本はそういう平和外交の可能性を今でも追求しているわけですけれども、これは日本として大いにやるべきことだと思っております。
武力を使うよりは、できるだけ心と心を通わせるような、対話をますます活用すること。高い立場から説教するよりは静かに、流暢な雄弁であるよりは訥々とした話し方で、できれば現地語を話すような形でやるというのは効果がありますし、そのほうが望ましいのではないかと思います。大きな目的は国際的に国連の場で多国間で成立できるかもしれませんけれども、具体的にどの紛争においてどういうやり方をするべきかについては各国や各NGOの人たちが、いちばん自分にふさわしいやり方を見いだしてやればいいと思います。そういう道はいろいろ日本の前にも沢山開かれているのではないかということを申しあげて、私の今日の拙い話に代えさせていただきたいと思います。
私のこのスケッチ的な駆け足の話は、あとで機会がありましたら多少説明させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
●明石 康 氏 プロフィール
公益財団法人国際文化会館理事長。1931年生まれ。東京大学卒業後、バージニア大学大学院、フレッチャースクール、コロンビア大学大学院。日本人初の国連職員。カンボジアや旧ユーゴスラビアの国連事務総長特別代表、人道問題担当国連事務次長などを歴任。主な著書に『国際連合―軌跡と展望』(岩波新書)、『国連ビルの窓から』(サイマル出版会)、『戦争と平和の谷間で―国境を超えた群像』(岩波書店)、『「独裁者」との交渉術』(集英社新書)など。