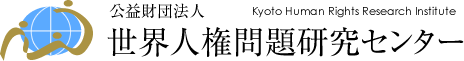エキスパートコメント
新地開発について考える
2024年10月29日
(公財)世界人権問題研究センター
プロジェクトチーム2リーダー
小林 丈広
寛文新堤の造築
世界人権問題研究センターが現在地に移転して約1年。京都駅に程近い、京都最大の被差別部落のまっただ中、眼下に高瀬川を臨む、人権と歴史について考えるには、これ以上ない好立地である。
森鷗外が小説「高瀬舟」を発表するのが1916年(大正5)、高瀬川の舟運が廃止されるのが1920年。角倉了以らが高瀬川を開削したのが1610年代と伝えられるので、京都物流の大動脈はその300年間の歩みを止めた。ちょうどその頃、都市計画事業の一環として、河原町通を拡幅するか、木屋町通か寺町通か、沿岸の旅館や廃業した船頭、周辺住民を巻き込んだ論争が展開するが、結局、河原町通の拡幅に決まる。木屋町通の拡幅に決まれば、高瀬川は埋め立てられていたことであろう。舟運が廃止となった高瀬川に水を流す必要はないのであり、流し続ければ、浚渫や塵芥の回収、ときには悪臭対策も必要となる。埋め立ててしまえば、そうした費用は必要なく、京都市内に新たに活用できる土地が生まれる。そうした考え方もあったのである。
さて、この高瀬川と鴨川は高瀬川の北の起点である二条通から、並行して流れ下っているが、五条大橋のあたりでかなり近付く。とはいえ、現在は高瀬川と鴨川とではかなり高低差があるので、鴨川がよほどの大氾濫を起こさない限り、両川が一体になることはない。
ただ、こうした鴨川と高瀬川との関係は、寛文年間(1670年前後)に鴨川に堤防が築かれてからのもので、それまでは、大水が出れば鴨川と高瀬川が一体化することは少なくなかったものと思われる。とくに、五条大橋以南の高瀬川は鴨河原を流れていたといっても良いほどで、高瀬川沿岸に安定的に人が住むことはできなかった。
七条新地の開発と六条村の移転
寛文新堤は、繰り返される鴨川の氾濫から京都市民を守るという意味があったが、そのおかげで、沿岸に新しい住宅地(新地)を開発することが可能になった。図は、本研究で分析対象としている今村家文書に含まれるものであるが、これらの文書によって、鴨川と高瀬川の間、現在の五条大橋と七条大橋の間の開発の経緯が詳しくわかるようになったのである。
当時、五条大橋は存在していたが、七条通には常設の橋は架かっていなかった。七条通は妙法院(方広寺や三十三間堂などを包摂する寺院群)で突き当たりとなっており、人通りが多いとはいえなかったが、この地域一帯の領主妙法院は新たな収入源を求めて新地開発を進めようとしていたのである。新地開発は七条通から北に向かって進められ、まずは七条新地が造成された。1700年代(宝永年間)のことである。
ところが、七条新地の開発が進むと、その北に被差別民集落があることが問題となる。妙法院としてはさらに開発を進めたいところであったが、被差別民には皮革業や警刑吏役のような公務など固有の存在意義があり、単に立ち退きを求めれば済むというものではなかった。移転先を含め、町奉行所や被差別民との交渉が必要であり、それぞれが納得できる計画が求められたのである。
その結果、被差別民は七条通のすぐ南に移転させられることになり、その跡地も新地開発の対象となったのである。移転させられた被差別民集落は、七条通よりも南にできたにもかかわらず、故地にちなんで六条村と呼ばれ、それが現在世界人権問題研究センターが立地する被差別部落の最初の核となった。
七条新地の遊所化
1710年代(正徳年間)、七条新地の北に六条新地が開発され、六条村が七条通の南に移転させられると、さらに北に向けての開発が検討される。1750年代(宝暦年間)に行われた五条新地(橋下)の開発がそれで、七条新地の開発から半世紀かけて五条大橋までの新地開発がなされたのである。
こうして開発された新地は、本来、新しい住宅地という意味であり、実際には開発者が家賃収入を目的として建築した借家群であった可能性が高い。領主である妙法院は、開発者から地代を受け取っていたのである。
江戸時代の京都では、市街地に隣接した寺社の境内や門前において、こうした地代目的の開発が行われており、建仁寺領については小出祐子氏の研究が、その一連の経緯を明らかにしている(「江戸時代の京都建仁寺境内における新地開発―六波羅新地の成立と借屋の形成―」『京都という地域文化』雄山閣、2020年など参照)。ただ、その研究によれば、開発された新地が必ずしも借家人で埋まるわけではなく、また高い家賃収入が保証されているわけでもない。結果的に、小規模で粗末な長屋群ができたり、空き地が目立ったりした。本来、都市の商業活動を支える商人や職人の入居を期待していた借家群であるが、次第に貧民窟のようになっていくのは避けられなかった。あるいは、売春を目的とする安宿とわかっていても借家を貸すこともあったであろう。新地が遊所と同義語のようにみなされるようになるのは、そうした事情があったと考えられるのである。七条新地もその例に洩れることはなかった。
坂本龍馬が、のちに妻となるお龍と出会ったのは、七条新地の扇岩という宿屋だったという。父親を亡くしたあと、お龍の一家はあちこちで手伝いや奉公をして世過ぎをしており、新地にはそうした働き方をしている者も多かった。
七条新地の近代
江戸時代の京都の特徴は、新地に展開した遊所の肥大化であり、社寺への参詣客や坂本龍馬のような志士、富裕な市民などがその繁盛を支えていた。明治維新直後の京都府は、そうした実態を問題視し、女紅場を設けて、遊所で働いている女性に読み書きや裁縫などの技術を伝えようとしたが、次第にそれも形骸化し、芸能を伝習する場に変貌していった。
もともと、七条通より北側の一画を意味していた七条新地であるが、その北の六条新地、さらにその北の五条橋下までもが遊所化すると、五条通、鴨川、七条通、高瀬川に囲まれた一帯を七条新地と呼ぶようになった。
昨年度、筆者のゼミで卒業論文を提出した釜ヶ沢みどり氏によれば、近代京都の遊廓の中でも、芸妓が多かったのが上七軒、祇園甲部、先斗町などで、娼妓が多かったのが七条新地、五番町などであった、また、もともと娼妓が多いとはいえなかった島原も、1920年代から増え始め、宮川町をしのぐようになる。これらの地域の中でも、七条新地の娼妓の増加は顕著で、1910年代には800人を超え、1920年代には1400人に迫ったという。多くが子供の頃に身売りされてきたと考えられるのに、地元の小学校ではとくに女子児童が増えている様子はなかった。女紅場で目指そうとしていた遊所の女性に対する教育は、時代が変わってもなかなか実現しなかったのである。
また、1920年代以降、京都にもカフェーやダンスホールなどが増え始めると、木屋町通や河原町通などの繁華街では雇仲居(やとな)や「カフェーの女給」による性的サービスが広がった。娼妓がほとんどいなかった先斗町には雇仲居や女給が進出し、娼妓が多かった七条新地には雇仲居は進出できなかった。しかし、格式や行儀作法を仕込まれて育った芸妓や娼妓は、女給の接客態度に批判的であり、それぞれの客層も異なっていたのである。
さて、以上のような歩みを持つ七条新地であるが、戦後の売春防止法の影響は大きかった。しかし、売春防止法によって姿を消したのは娼妓だけであり、娼妓の一部は、芸妓や雇仲居、女給などに姿を変えて生き残ったのである。